小笠原・西ノ島新島に初上陸した研究者グループが見たものは頼もしく生きる動植物だった!

2013年11月からの噴火によって拡大を続け噴火前の12倍にもなった西ノ島。
ようやく活動も収まり、2016年8月の警戒範囲の縮小を受け、10月20日に研究者グループが噴火後初めて島に上陸した映像が公開されました。
スポンサーリンク
今年の4月と5月には西ノ島の周囲をクルーズするツアーも開催され、上陸調査も今か今かと待たれていました。
上陸したのは火山や地質、鳥類の専門家14名。
火山の状態や地質調査のための溶岩の採取や、アホウドリなどの鳥類の営巣状況などの生態調査。
地震計や空振計などの観測機器、鳥達の声を録音する音声録音装置を設置などが設置され、これからの西ノ島の火山活動の観測や、生態系がどのようにしてつくられていくのかが観察、研究されていくことになるとのこと。
出典:海上保安庁
海洋島の進化の過程をこれから何十年、何百年と記録していく。
途方も無い事ですが、何百年後かの人たちがこれらの記録映像を見て「この島の始まりはこんな感じだったんだ」と思うのかな?なんて考えると、未来の人と繋がる気がしてなんだかいいですね〜。
映像を見ると、既に卵を抱いて営巣しているカツオドリ?の姿があります。
上陸する以前より、無人調査などで30羽ほどの海鳥が営巣しているのが確認されているそうですので、もう既にこの島から巣立った鳥たちもいるのかもしれないですね。
そして研究者が上陸して観測機器の設置をしている場所には植物が生えていたので、僅か残っていた西ノ島の部分ですね。
出典:海上保安庁
噴火から3年経っても青々と茂っているということは、噴火活動中も生育を続けていたんですね。
西ノ島の今回の噴火活動の映像では、赤い溶岩を噴き出す様子が写っていて僅かに残っているとはいえ、熱風と火山ガスで壊滅してもおかしくないんじゃないかと思っていたので何だか凄いです。
出典:小笠原観光局
そういえば、西ノ島には噴火前にはどのような動植物が島に存在していたんどろう?と気になります。
調べてみると、西ノ島は1973年にも噴火しておりその後の調査でも植物は、沖縄の海岸でも見かけるハマゴウなど6種、動物はカツオドリ、ウミツバメ、オナガミズナギドリなど12種の海鳥が確認されていたそうです。
40年かけてできた島の生態系
たったこれだけ?なのか、こんなに?なのか。
今は豊かで独自の進化をしてきたと言われる小笠原諸島も何百年、何千年の時間をかけてつくられたもの。
人のモノサシでは計れない雄大な時の流れの中ではほんの一瞬なんだと思うと、何だか日常の些細なことでストレスを溜めているのが、ホントにちっぽけなことだなあ~なんて思ったりしますね。
小笠原諸島へ!「新おがさわら丸」船の予約方法と旅行日程の立て方2016
沸騰ワード10・沸騰島ってどこ?小笠原諸島女性一人旅増加の理由を予想してみました!
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







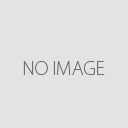
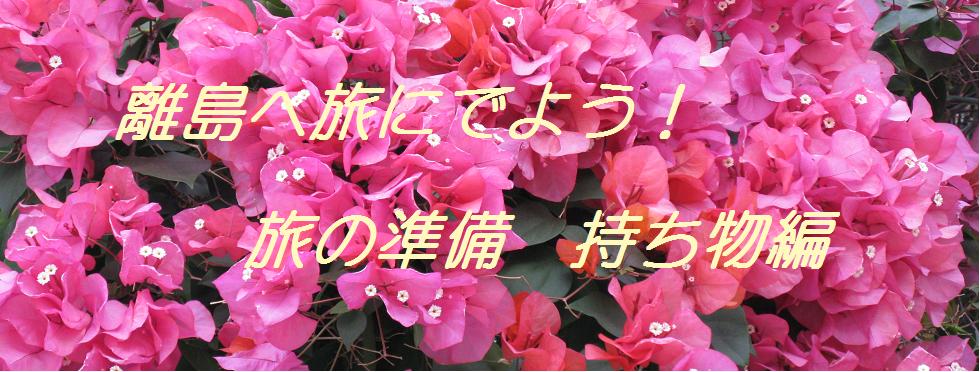
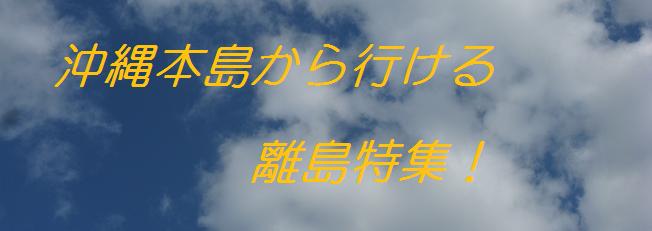


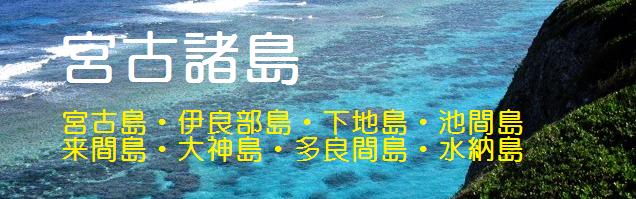












この記事へのコメントはありません。